1章:30代共働き世帯の「キャリア」と「育児」の綱渡り
まずは、普段感じるであろう“仕事」と“育児”という2つの大きな軸を整理しておきます。
30代はキャリア形成の重要な時期です。昇進や転勤、プロジェクト参加など、仕事のステージが変わることも多いでしょう。一方で、子どもは幼児期に入り、食事・トイレ・保育園・習い事など、育児の忙しさも急増します。共働きだからこそ、「どちらが今日子どものお迎えにいくか」「この月は家計がタイトだから副業も…」といったやりくりが常に求められます。
このような状況で頼りになるのが、「社会保障制度」です。社会保障制度というのは、病気・高齢・失業・介護といった人生のリスクに備えるため、社会全体で支えあう仕組みです。そして、その中で「雇用保険」は、失業時だけでなく、働き続けることや能力を伸ばすことも支える役割を担っています。たとえば、育児のために休業する、その間の収入が完全に途絶えると家計が大きく揺らぎ、キャリアにブランクができるリスクもあります。雇用保険から「育児休業等給付」や「教育訓練給付」があることで、共働き世帯にとっての強いセーフティネットになるのです。
しかしながら、制度は“申し出なければ受けられない”という原則があります。つまり「知っておく・制度を使えるようにしておく」ことがとても重要。ここから、特に使うべき給付制度を整理します。
2章:育児休業給付金 ― 長期休業を支える経済的基盤
育児のために仕事を休む。これができるのも、給付制度があるからこそ。ここでは、いわゆる「育児休業給付金」の内容を見ていきます。
① 受給要件と期間
この給付金を受けるには、主に次のような要件があります。
-
雇用保険の被保険者であること。具体的には、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある一般被保険者または高年齢被保険者であること。
-
育児休業を、原則として「子が1歳になるまで(誕生日の前日の前日まで)」取得すること。さらに、両親が交代して取る「パパ・ママ育休プラス」によって、子が1歳2か月まで延長されるケースもあります。
-
また、保育所に入れないなどの事情がある場合には、最長「子が2歳になる前日」まで延長できる制度もあります。
-
休業期間中の賃金が、休業開始前の賃金と比べて80%未満であること。就業日数が10日以下(もしくは80時間以下)であること。
このような要件を満たせば、育児休業給付金が支給されます。共働き家庭の場合、どちらか一方・または両方が対象になる可能性があります。
② 支給額と上限
支給額もしくは支給率は、次のように段階があります。
-
育児休業開始から6か月(180日)に相当する期間までは、休業開始時賃金日額の67%相当額。
-
6か月経過後は、休業開始時賃金日額の50%相当額。
-
給付金は「非課税」であり、また育児休業期間中は、社会保険(健康保険・厚生年金保険料)が免除される手続きもあります。これにより、休業前の手取りと比較すると「実質的に手取りの約8割程度」が支給されるという見方もあります。
-
上限額についても定めがあり、例えば30日分(支給日数が30日の場合)の上限額などが公表されています。
たとえば、直近6か月の賃金合計が100万円(つまり月約16.7万円)という例では、休業開始から6か月間の月額給付は“67%相当”で、約11万1千円程度という計算例もあります。
③ 共働き家庭における活用ポイント
共働きの世帯では、次のようなポイントを押さえておくと、制度活用の幅が広がります。
-
両親で育児休業を“交代して”取得することで、子どもが1歳になる前後まで休みを分割できるという制度(パパ・ママ育休プラス)が使えるケースがあります。
-
休業期間中、賃金が著しく低下することで、家計が揺らぐことがありますが、給付金に加えて社会保険料免除が働くため大きな支えになります。
-
申し出・手続きが必要です。会社と相談し、「休業開始日」「申請期限」「勤務形態」「給付対象かどうか」を事前に確認しておきましょう。
-
休業開始月から2か月ごとに申請をするという実務もあります。
-
休業前に副業やアルバイト等をしていた場合、それらの収入によって給付額が減額される可能性もあるため、休業中の働き方も注意が必要です。
このように、育児休業給付金は、「子育てのために仕事を休む」際の安心材料として非常に力強い制度です。特に共働き家庭では、家計を見通しながら休業を取得することが大きなポイントです。
3章:2025年施行!子の出生直後と時短勤務を支える新給付
制度は改正・拡充が進んでおり、2025年(令和7年)10月1日以降に新たに創設される給付も共働き世帯にとって注目の内容です。
① 出生後休業支援給付金
この給付は、まさに「子が生まれた直後」「両親ともに育児に関わること」を経済的に支援するための制度です。
| 制度名 | 出生後休業支援給付金 |
|---|---|
| 対象期間 | 母親は子の出生日または出産予定日のうち遅い日の翌日から16週間以内。父親は子の出生日から8週間以内。 都道府県労働局+1 |
| 支給要件 | 両親ともに通算14日以上の育児休業等を取得すること。※配偶者が雇用保険の被保険者でない場合や、シングルマザー・ファザーの場合は配偶者の休業取得要件なし。 都道府県労働局+1 |
| 支給額 | 従来の育児休業給付金(67%)に加え、賃金日額の13%を上乗せ支給。つまり、合計で約80%相当が支給される設計。 バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」+1 |
| 支給期間 | 最大28日間まで。 都道府県労働局+1 |
この制度のポイントは、「出生直後の育児参加」を推進するため、経済的な安心を高めることです。共働きのご家庭なら、特に「産後、どちらが育児に専念するか」「二人でどこまで休業を分担するか」という設計を立てやすくなります。
② 育児時短就業給付金
子どもがある程度成長して、育児と仕事を両立させる時期には「時短勤務」が選択肢となります。ただ、時短勤務にすると賃金がどうしても下がる可能性があり、その低下を補う給付がこちらです。
-
対象者:育児休業から引き続き、子が「2歳に満たない」状況で「時短勤務をして」いる労働者。 JAIFA 公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会 |
-
支給要件:時短勤務後の賃金が「時短前の賃金の90%以下」となった場合に対象。 JAIFA 公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会 |
-
支給額:対象月の賃金に対して、賃金低下率に応じて給付率が設定され、「時短後の賃金が90%以下の場合は10%」支給。さらに、時短後の賃金が90%を超えて100%未満の場合は、低下率に応じて支給率が逓減。 JAIFA 公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会 |
この制度も、共働き家庭の“仕事を続けながら育児”という選択を支えるものです。時短勤務を選ぶことで賃金が下がり、家計が厳しくなる懸念を少しでも和らげてくれます。
活用にあたってのポイント
-
どちらの給付も、新制度ゆえに「いつから」「どんな条件で申請できるか」を会社と確認しておくことがカギです。
-
給付対象となる時期や条件(対象期間/取得日数/賃金の低下率など)をしっかり把握しておきましょう。
-
時短勤務を選ぶ場合、「いつから」「何時間時短にするか」「時短後の賃金はいくらになるか」というシミュレーションを立てておくと安心です。
-
両親で育児休業を分担する場合、双方の勤務先との調整が不可欠。制度の知識を共有しておきましょう。
4章:育児後のキャリア再構築!教育訓練給付の賢い活用
子育ての期間が落ち着いてきた、あるいは育児休業から復帰したというとき、30代として気になるのは「このままキャリアを続けられるか」「もっとスキルアップできないか」ということです。ここで役立つのが、雇用保険の「教育訓練給付」です。
① 教育訓練給付の種類
主に次の3種類があります。条件や給付率・上限額が異なります。
-
一般教育訓練給付金:在職中または離職中の被保険者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けると、教育訓練経費の20%が支給され、上限額は10万円。
-
特定一般教育訓練給付金:再就職・早期キャリア形成に資する講座(業務独占資格・デジタル系など)が対象。給付額は教育訓練経費の40%(上限20万円)で、さらに受講修了後、雇用された場合は追加で10%(上限5万円)が支給される。
-
専門実践教育訓練給付金:高度な専門知識・技能を習得するための訓練(最大3年間)。給付額は教育訓練経費の50%で、最大1年間あたり40万円(最大120万円)。さらに受講修了から1年以内に資格取得・雇用された場合には追加20%が支給され、合計70%(最大168万円)になる。再就職後の賃金が5%以上上昇した場合は、支給率80%(最大192万円)になるケースも。
※制度の詳細・利用可能講座は、都度確認が必要です。
② 新設の教育訓練休暇給付金(2025年10月1日~)
さらに、2025年10月1日からは「教育訓練休暇給付金」という新制度もスタート予定です。これは、在職中の被保険者が教育訓練を受けるための休暇(教育訓練休暇)を取得し、一定の要件を満たした場合に支給されるものです。給付額は、失業時に支給される「基本手当」と同額とされ、休暇取得可能期間は被保険者期間に応じて“90日・120日・150日”という3段階で設定される予定です。子育てによるブランクを恐れず、「スキルアップに集中する時間」を持つという選択を後押ししてくれます。
③ 共働き世帯ならではの活用ヒント
-
育児休業明け、時短勤務で少しずつ仕事に慣れながら、その合間に短期のスキルアップを狙う――こうした設計が可能です。
-
将来、転職を視野に入れたり、リモート・副業等も視野に入れているなら、「特定一般」や「専門実践」給付を活用しておく価値があります。
-
教育訓練休暇給付金のように、休暇をとりながらスキルを磨くという選択肢も頭に入れておくことで、将来的な働き方の幅が広がります。
-
受講対象の講座・条件(雇用保険への加入期間、修了要件、雇用要件など)を事前に確認しておくことが安心につながります。
5章:結びにあたって ― 公的支援をしっかり活用し、仕事と子育ての安心を確保
30代の子育て世代にとって、仕事も育児もどちらも「手を抜けない大切な時間」です。そんな中で、「休業」「時短」「スキルアップ」といった選択肢が制度によって支えられているということは、非常に大きな安心材料です。改めて、重要なポイントを整理しましょう。
【再確認すべき重要ポイント】
-
育児休業給付金:育児休業開始から6か月までは賃金の約67%、その後は約50%相当額が給付され、給付は非課税・社会保険料免除もあり、実質的に休業前手取りの約8割が維持できる場合もあります。
-
出生後休業支援給付金(2025年創設):子の出生直後に、両親がともに育休を取得することで、従来の給付に+13%上乗せ、最大28日間で合計給付率80%相当を実現。共働き家庭の育児参加を後押しします。
-
育児時短就業給付金(2025年創設):子が2歳未満で時短勤務を選択した際、時短後の賃金が90%以下になった月について、時短前賃金の低下率に応じて最大10%の給付が支給されることで、家計とキャリアの両立を支えます。
-
教育訓練給付(および新制度の教育訓練休暇給付金):育児休業明け・時短勤務中・将来のキャリアを見据えた時期に、在職中・離職後のスキルアップを支える制度。特定講座・高度講座で、費用の20%~最大70/80%まで給付されるケースもあります。
これらの制度を上手に活用することで、「育児に時間を割きたい」「キャリアを維持・成長させたい」という両立の矛盾を、制度の力を借りて少しずつ現実に近づけることが可能です。共働きという選択をされている30代のご夫妻だからこそ、制度を「知っておく」「使えるようにしておく」ことが、安心してライフステージを進める鍵となります。
最後にもう一つ。雇用保険制度は、働く人がそのキャリアを安心して継続し、子育てなどのライフイベントと両立できるよう、法改正を重ねて進化しています。こうした制度を活用するには、「自ら申し出る」ことが大前提です。会社の制度(育児休業や時短勤務)を確認し、必要な申請書類・スケジュール・給付要件を整理しておきましょう。
これから、子育てと仕事の両立に向けて、少しでも安心できる土台をつくっていってください。応援しています。
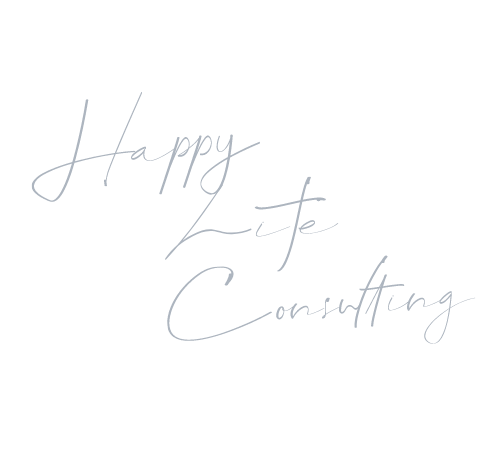
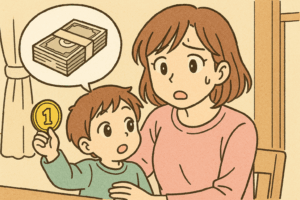
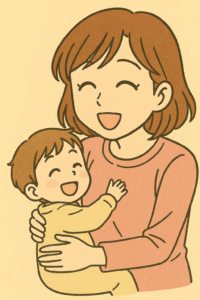
 前の記事
前の記事



