はじめに:なぜ年金を知っておくことが大事なの?
 「うちはまだ子どもも小さいし、老後なんてまだ先…」
「うちはまだ子どもも小さいし、老後なんてまだ先…」
そう感じる方も多いかもしれません。
でも、年金制度は“今”から知っておくことが、将来の安心につながる大切な知識なんです。
日本には「社会保障制度」という、みんなが安心して生活できるように国が整えた仕組みがあります
その中でも「社会保険制度」は、病気・ケガ・失業・高齢・介護といった人生のリスクに備えるためのもの。
つまり、もしもの時に“お互いに助け合う”ための制度です。
その柱のひとつが年金制度。
年金には次の3つの役割があります。
- 障害を負った時の生活を支える「障害年金」
- 家族を亡くした時の生活を支える「遺族年金」
- 高齢になってからの生活を支える「老齢年金」
ただし、年金は自動的にもらえるわけではありません。
受け取るためには、自分で「裁定請求」という手続きをする必要があります。
だからこそ、早めに仕組みを知っておくことが大切なんです。
- 年金の全体像:「2階建て構造」で支え合う仕組み
日本の年金制度はよく「2階建て」と言われます。
下の“1階部分”が国民年金(基礎年金)、上の“2階部分”が厚生年金です。
(1)それぞれの役割
国民年金(1階)
20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。自営業や学生、フリーランスも対象です。
厚生年金(2階)
会社員や公務員など、給与をもらって働く人が加入します。国民年金に上乗せされる形です。
さらに、国民年金の加入者は3つのタイプに分かれます。
- 第1号被保険者:自営業・フリーランス・学生など(自分で保険料を納める)
- 第2号被保険者:会社員・公務員(給料から天引き)
- 第3号被保険者:第2号に扶養されている専業主婦(夫)など(保険料は免除)
(2)「世代間で支え合う」仕組み
日本の年金は、「今の現役世代が払ったお金を、今の高齢者に渡す」仕組み=賦課(ふか)方式で成り立っています。
つまり、私たちが支えている“今の高齢者”の分を、将来は“次の世代”が支えてくれるという考え方です。
また、物価の変化に合わせて年金額も見直されるため、長生きしても一生もらえる安心感があります。
- 老齢基礎年金:誰でももらえる「1階部分」
(1)もらえる条件と金額
老齢基礎年金は、原則65歳から受け取れます。
受給するには、10年以上保険料を納めていることが条件です(免除期間も含む)。
40年間すべて納めた場合(満額)は、
👉 **年間831,700円(令和7年度時点)**がもらえます。
納めた期間が短いと、その分少なくなります。
(2)年金額の見直し
年金額は、物価や賃金の変動に合わせて毎年見直されます。
また、少子高齢化が進む中で年金制度を長く続けるための「マクロ経済スライド」という仕組みも導入されています。
- 老齢厚生年金:「働いた分だけ上乗せ」される2階部分
(1)もらえる条件と金額
厚生年金は、会社などで働いていた期間が1か月でもあれば対象になります。
支給は原則65歳から。
金額は「働いていた期間」と「給料の平均額」で決まります。
(2)家族への加算(加給年金)
20年以上厚生年金に入っていた人が65歳になると、
扶養している配偶者(65歳未満)や子どもがいる場合、加給年金が上乗せされます。
令和7年度の配偶者加給年金は 239,300円。
配偶者が65歳になると、この分はその人の基礎年金に振り替えられます。
- いつからもらう?年金の受け取り時期と働き方
(1)繰上げ・繰下げ受給
年金は原則65歳からですが、
自分のライフプランに合わせて受け取り時期を調整できます。
- 早めにもらう(繰上げ) → 1か月ごとに 0.4%減額
- 遅らせてもらう(繰下げ) → 1か月ごとに 0.7%増額
今は60歳から75歳までの間で自由に選べます。
「もう少し働くつもりだから、遅らせて増やそう」という選択もアリです。
(2)働きながら年金をもらう場合
60歳以降も働いて年金をもらう場合、「在職老齢年金制度」が適用されます。
給料と年金の合計が一定額を超えると、一部が減額・停止されることがあります。
ただし、2025年度からは基準が51万円に引き上げられ、以前より働きやすくなりました。
- 年金記録の確認と覚えておきたい制度
(1)ねんきん定期便をチェック
毎年、自分の誕生月に「ねんきん定期便」が届きます。
これを見ると、これまでの納付履歴や将来の見込み額がわかります。
誤りがないか、毎年チェックしておくことが大切です。
(2)離婚時の年金分割
離婚した場合、結婚中の厚生年金を分けられる制度があります。
- 夫婦の合意で分ける「合意分割」
- 専業主婦(夫)期間を自動で半分ずつにする「3号分割」
どちらも、離婚後2年以内に手続きが必要です。
 (3)生活が厳しいときの支援
(3)生活が厳しいときの支援
収入が一定以下の方には、**「老齢年金生活者支援給付金」**が上乗せされる制度もあります。
年金だけでは不安な方の生活をサポートする仕組みです。
- まとめ:知っておくことで未来の安心が変わる
年金は、「もらえる」「もらえない」ではなく、
どう活用して、どう備えるかの話です。
公的年金は、世代で支え合う仕組み。
ただし、受け取るためには自分で「裁定請求」という申請が必要です。
受給開始の年齢を自分で選べる今、
自分たちの働き方・家計・老後の暮らしに合わせて、賢く準備していくことが大切です。

📘 まとめポイント
- 年金は「2階建て構造」(国民年金+厚生年金)
- 原則65歳から受給、繰上げ・繰下げもOK
- 「ねんきん定期便」で記録確認を忘れずに
- 離婚時や低収入時も支援制度あり
- 将来の安心のために、まず「知ること」からスタート!
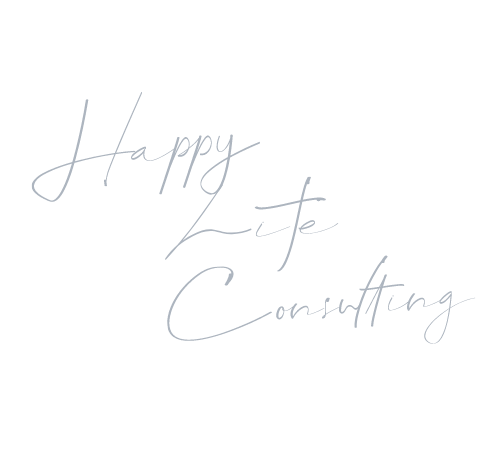
 前の記事
前の記事



